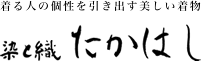トップページ > 商品紹介 > 竺仙 長板本染中形浴衣(大小あられ・藍地)
竺仙 長板本染中形浴衣(大小あられ・藍地)
商品説明
さらりとした綿縮に、「長板中形」と呼ばれる伝統的な技法で、大小あられと菖蒲が染められています。藍と白、シンプルですっきりとした、まさに江戸好みの浴衣地です。
長板中形(長板本染とも)は、板場に渡した長板に生地を張り、両面に寸分違わず糊置きをする大変高度な技法です。白と本藍のコントラストが美しい江戸好みの伝統的な技法ですが、年々職人が減り生産反数も少なくなっています。

博多織の半巾帯を合わせて…
こちらの反物は、大小あられと菖蒲、片面ずつ異なる型紙を使い染められています。浴衣としてはもちろんですが、自然布や博多織の八寸などを合わせて頂くと、「夏の気軽な小紋」そう表現する方がしっくりくるコーディネイトです。
上質な生地と昔ながらの染めに拘った竺仙の浴衣。江戸末期から磨かれてきたそのデザインはシンプルですが、不思議と飽きることがありません。大人の浴衣として、長く着て頂けるきっとそんな一枚になるはずです。お手持ちの帯とのコーディネイトなどお気軽にご相談下さい。
■お仕立てについて
お手入れ時の縮み軽減のための水通し後、弊店にて裁ち合わせを行います。その後弊店の基準に合格した国内の熟練の和裁士さんにお仕立てをお願いしています。寸法のご相談などございましたら、お申し付けください。
■お手入れについて
ご家庭での水洗いが可能です。洗剤は使わず、やさしく押し洗いして下さい。色落ち、縮みが気になる場合は、ドライクリーニングをおすすめします。いずれも自己責任でのお手入れとなりますので、品質表示をよくご確認下さい。
■色について
HP上の商品の色は可能な限り、現品に近づけてはおりますが、お客様のご使用のパソコン、OS、ディスプレイ(モニター)により色味が異なる場合がございます。何卒ご理解頂きますよう、お願いいたします。*パソコンで綺麗に表示されない場合、iphoneやスマートフォンからアクセスして頂くと、綺麗に表示される場合があります。
■お手元での商品確認サービス
こちらの商品はお手元で実際の商品をご確認いただけます。尚サービスご利用には仮決済が必要です。詳細はオンラインショップをご覧ください。
■在庫について
実店舗でも商品を販売しておりますので、お申込み頂いても売り切れの場合がございます。先着順にご紹介いたしますので、何卒ご了承下さい。
■長板本染中形について
長板本染中形は、長板を用い布地の表裏両面に寸分違わずに型付け(防染糊を置く事)をし、本藍で浸染するという、江戸時代中期末より行われている技法です。中形は、大紋・中形・小紋と分かれる模様の大きさからの名称で、浴衣に染められることから、浴衣の代名詞となっています。江戸の伝統を継承した、小紋と言えるほどの精緻な模様を錐彫りで表した中形を特に小紋中形といいます。 一反ずつ念入りに型付けされ、本染めされた伝統的な江戸浴衣は、堅牢でありながらも優美で、まさに夏のきものの主役にふさわしい物です。*竺仙説明文より
竺仙 長板本染中形浴衣(大小あられ・藍地)
- 【素材】
- 綿100%
- 【生地巾】
- 約36.2cm
- 【生地丈】
- 約12m
- 【価格】
- 売切御礼
この商品をみたお客様は、こんな商品もみています
-
程よい透け感のある女郎花色の地に、躍動感のある葵文が染められています。絞りの柔らかな輪郭と、墨書き(カチン)による細やかな筆致が美しい、森健持さんの辻が花九寸名古屋帯です。辻ヶ花染めは室町時代から江・・・
-
まるで織物のような細かな模様。これは、糸のように細くした竹を丁寧に手で編んで繊細に表現した竹細工です。タイのバンコク郊外、自然豊かな工房で女性を中心とした職人たちが、竹を細かく裂いたり、染めたりし・・・
-
野村半平(のむらはんぺい)氏をご存知でしょうか。明治37年結城市で生まれた野村半平氏は、高等小学校を卒業後、結城紬の職人の道へ。戦中の奢侈禁止令から結城を守り、国の重要無形文化財指定に奔走した、まさに・・・
-
緑みを帯びた花浅葱色の地に、縞と経絣、細かな浮織模様が織り出されています。「よるの森」と名付けられた河野香奈恵さんの九寸名古屋帯です。河野さんは東京都青梅市出身。女子美術大学芸術学部工芸学科を卒業・・・
-
まるで織物のような細かな模様。これは、糸のように細くした竹を丁寧に手で編んで繊細に表現した竹細工です。タイのバンコク郊外、自然豊かな工房で女性を中心とした職人たちが、竹を細かく裂いたり、染めたりし・・・
-
白地にさわやかな薄紫色を染め上げた「雪花絞り」の浴衣です。染まり上がりの柄が雪の結晶のように見える為、“雪花”と呼ばれています。雪花絞りは一反の白生地をアイロンをかけながら丁寧に折りたた・・・