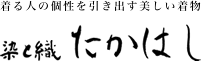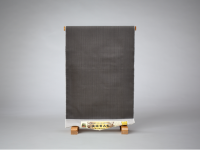トップページ > 商品紹介 > 工芸会 釜我敏子 型絵染め九寸名古屋帯(野ばら)
工芸会 釜我敏子 型絵染め九寸名古屋帯(野ばら)
商品説明
「野ばら」と名付けられた、日本工芸会正会員 釜我敏子(かまがとしこ)さんの型絵染め九寸名古屋帯です。
柔らかな乳白色の地に、伸びやかな意匠で抽象的な“野ばら”が染められています。“型絵染め”と言う技法の制約を忘れてしまうほど、巧みに繰り返されたデザイン。水色・薄紫・淡桃色・鉄紺などそれぞれの挿色が、透明感のある暈しと濃淡で表現されています。
釜我敏子さんは、1938年福岡市生まれ。県立福岡高校を卒業後、お母様の勧めもあり染めをはじめられます。鍋島更紗の鈴田照次氏(現人間国宝 鈴田滋人氏の父)の作品に感銘を受け、長板中形の松原利男氏らに師事。1970年西部工芸展、1975年伝統工芸日本染織展、1976年の日本伝統工芸展にそれぞれ初入選。 1979年には日本工芸会正会員に認定。東京国立近代美術館の「現代の型染展」において、日本を代表する25人に選出されるなど、現代を代表する型絵染め作家です。
「型絵染め」という言葉は、1956年に芹沢銈介氏が人間国宝に認定された際、その他の型染めの技法と区別するために考案された名称です。技法的には沖縄の紅型とよく似ています。
釜我さんをはじめ、作家と呼ばれる方達の作品は図案、型彫り、糊伏せ、彩色、地染めまで基本的に全て一人で行います。そのため分業の多い友禅や小紋染などとは違い、作家さんの個性や想い、感性が作品に強く表れます。
柔らかな紬地に、六通(タイコから前腹まで)でたっぷりと柄が染められていますので、タイコ柄の苦手な方も安心してお締め頂けます。結ぶ位置を少しずらせば、表に出てくる柄が変わり帯の表情が変化します。またタレ先は、水色の無地場(1枚目の写真参照)と柄部分(5枚目の写真参照)どちらかをお選び頂けます。どちらの場合も釜我さんの落款(サイン・8枚目写真)は太鼓裏に隠れるようになります。
小紋や紬、お召、木綿などに合わせて、お楽しみ頂ければと思います。お手持ちのお着物とのコーディネイトなどお気軽にご相談下さい。
■お仕立てについて
弊店にて検品後、弊店の基準に合格した国内の熟練の和裁士さんにお仕立てをお願いしています。寸法のご相談などございましたら、お申し付けください。
■お手入れについて
日常のお手入れは、部分的なしみ落としで十分です。長期間の保存の前や、全体の汚れが気になる場合は、ドライクリーニングをお薦めしています。ご家庭での水洗いは出来ませんので、ご注意下さい。
■ガード加工について
ガード加工をご希望のお客様は、オンラインショップのプルダウンメニューより【+ガード加工】をお選びください。ご指定の無い場合の加工は、パールトーン加工となります。 その他の加工をご希望のお客様はご連絡をお願い致します。 ・シルクガード・ハジックガード加工等
■写真・色について
HP上の商品の色は可能な限り、現品に近づけてはおりますが、お客様のご使用のパソコン、OS、ディスプレイ(モニター)により色味が異なる場合がございます。何卒ご理解頂きますよう、お願いいたします。また染と織たかはしオンラインショップでは、その他の写真を多数掲載しております。ぜひご覧ください。
染と織たかはしオンラインショップ http://kimonotakahashi.shop-pro.jp
■お手元での商品確認サービス
こちらの商品はお手元で実際の商品をご確認いただけます。尚サービスご利用には仮決済が必要です。詳細はオンラインショップをご覧ください。
■在庫について
実店舗でも商品を販売しておりますので、お申込み頂いても売り切れの場合がございます。先着順にご紹介いたしますので、何卒ご了承下さい。
■釜我敏子(かまがとしこ) 略歴
1938年 福岡生まれ
1958年 福岡県立福岡高等学校卒業
1970年 第5回西部伝統工芸展 初出品/以後連続入選・受賞7回
1975年 第12回日本伝統工芸染織展 初出品/以後25回入選・受賞5 回・鑑審査員4回
1976年 第23回日本伝統工芸展 初出品/以後30回入選
1979年 日本工芸会正会員認定
2005年 福岡市文化賞受賞/福岡県春日市民文化賞受賞
2007年 第54 回日本伝統工芸展にて日本工芸会奨励賞受賞
工芸会 釜我敏子 型絵染め九寸名古屋帯(野ばら)
- 【素材】
- 絹100%
- 【生地巾】
- 約34.5cm
- 【生地丈】
- 約3.7m
- 【価格】
- 売切御礼
この商品をみたお客様は、こんな商品もみています
-
すっきりと…京友禅らしい瑞々しい白地に、手描き友禅で「藤」が描かれた塩瀬名古屋帯です。まず目に映るのは、おタイコに描かれた藤の美しい流れ。本歌はおそらく琳派でしょう。洗練された構図と配色、そ・・・
-
「緑草」と名付けられた、国画会加藤富喜さんの九寸名古屋帯です。加藤富喜さんは1972年生まれ。女子美術大学大学院を卒業後、毎年国画会へ出品。現在は国画会会員、そして母校の女子美術大学で非常勤講師を務め・・・
-
淡い白橡色(しろつるばみ)の地に、躍動感のある唐草文様が織り出されています。「金襴唐草」と名付けられた織楽浅野(しょくらくあさの)の名古屋帯。色彩を抑え、限られた色数から生まれる独自の世界観。糸使い、・・・
-
染織には人を魅了する不思議な力がある。たった一枚の布や裂が“人生を変える”そんな出会いになることがあるのです。今回ご紹介する築城則子さんも、そんな染織の不思議な力にみせられた一人。骨董店・・・
-
東京から南に約290㎞、伊豆諸島の最南端に浮かぶ常春の島、八丈島。自然豊かなこの島で、数百年もの昔から変わらず織り続けられている絹織物、それが本場黄八丈です。黄、鳶、黒、全てが島の草木から染められる、・・・
-
涼やかな淡い生成り色の地に、秋草と源氏香が織り出されています。夏らしい透け感を感じる紗の組織に、手織りで細やかに文様を表現した、すくい織夏九寸名古屋帯です。菊・葦・女郎花…すっきりと描かれた・・・