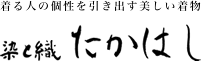滋賀喜織物・帯匠丹波屋
織物の聖地、京・西陣。
かつてはいたるところで機織りの音が聞こえ、帯地を中心に、盛んに織物が生産されていました。しかし現在では、その多くが西陣以外の場所で、そして、機械式織機によって生み出されています。“西陣・手機”の帯地に拘る、のこり僅かな機屋。その中で、今回は滋賀喜織物と帯匠丹波屋をご紹介します。
滋賀喜織物
滋賀喜織物(しがきおりもの)。
京都・大宮通今出川、まさに西陣の中心で滋賀喜の帯は織られています。玄関を入り、帳場を抜けた廊下までくると、その先の機場から小気味よい機織りの音が聞こえてきます。
「うちは手機(てばた)だけです。昔からそれだけしか出来ない。」工房を案内してくださった、当代の岩佐さんが仰られました。
本袋帯をはじめ、引箔、錦と綴地の併用など、手織りならではの帯地が機にかかり、少しずつ織り進められています。いずれも滋賀喜の歴史と職人の方々の技があってこそうまれる美しい帯地です。
京都・大宮通今出川、まさに西陣の中心で滋賀喜の帯は織られています。玄関を入り、帳場を抜けた廊下までくると、その先の機場から小気味よい機織りの音が聞こえてきます。
「うちは手機(てばた)だけです。昔からそれだけしか出来ない。」工房を案内してくださった、当代の岩佐さんが仰られました。
本袋帯をはじめ、引箔、錦と綴地の併用など、手織りならではの帯地が機にかかり、少しずつ織り進められています。いずれも滋賀喜の歴史と職人の方々の技があってこそうまれる美しい帯地です。
箔糸への拘り
滋賀喜織物では手機の技だけではなく、糸や箔糸などの素材にもけして妥協はありません。
安価な化学繊維の箔糸が主流になってしまった西陣で、和紙を柿渋で染め、漆で本金銀箔を張り、細く細く裁断した昔ながらの箔糸を変わらず使用しています。
この細い箔糸を通常の約1.5倍の密度(本数)で一本一本、竹ヘラで丁寧に打ち込んでいきます。滋賀喜を代表する引箔の帯地。驚くほど軽く、箔糸とは思えない柔らかな風合いです。
安価な化学繊維の箔糸が主流になってしまった西陣で、和紙を柿渋で染め、漆で本金銀箔を張り、細く細く裁断した昔ながらの箔糸を変わらず使用しています。
この細い箔糸を通常の約1.5倍の密度(本数)で一本一本、竹ヘラで丁寧に打ち込んでいきます。滋賀喜を代表する引箔の帯地。驚くほど軽く、箔糸とは思えない柔らかな風合いです。
帯匠丹波屋
帯匠 丹波屋(おびしょうたんばや)。
18世紀半ば、初代丹波屋甚兵衛が丹波国(現在の京都府中部)から西陣に移り住み、織屋を創業しました。当代で十代目、250年以上の歴史を持つ西陣の老舗機屋です。
京都・大宮通西裏芦山寺 京都らしい縦長の母屋の裏に、丹波屋の機場はあります。びっしりと並んだ機の下にふと目をやると、床板が外され地面が50センチ程掘り下げてあります。
「湿度を呼ぶために掘ってあるんですよ。昔の人はほんまよう考えはります」と、当代の清水さん。
「紋紙も今はフロッピーのとこが多いんですけどうちは昔のまま、紙の紋紙です。ほんまかさばりますけどね(笑)」
出来上がる数は決して多くありませんが筋の通った織味は信頼も厚く、洛風林などの別注品も手掛けています。
18世紀半ば、初代丹波屋甚兵衛が丹波国(現在の京都府中部)から西陣に移り住み、織屋を創業しました。当代で十代目、250年以上の歴史を持つ西陣の老舗機屋です。
京都・大宮通西裏芦山寺 京都らしい縦長の母屋の裏に、丹波屋の機場はあります。びっしりと並んだ機の下にふと目をやると、床板が外され地面が50センチ程掘り下げてあります。
「湿度を呼ぶために掘ってあるんですよ。昔の人はほんまよう考えはります」と、当代の清水さん。
「紋紙も今はフロッピーのとこが多いんですけどうちは昔のまま、紙の紋紙です。ほんまかさばりますけどね(笑)」
出来上がる数は決して多くありませんが筋の通った織味は信頼も厚く、洛風林などの別注品も手掛けています。
西陣・手織りに拘る
西陣に機械化の波が押し寄せた時代、多くの機屋が効率化や生産性を求め機械式織機を導入していきました。しかし滋賀喜織物と同じように、丹波屋もまた手織りの道を選択します。
“合理的な織物ではなく、美しい織物を手掛けたい”
そんな機屋としての誇りと、自分達の感性を信じる道を選んだ滋賀喜と丹波屋。
手織りであること。
西陣で織ること。
素材・意匠に拘ること。
常に新鮮さを求めること。
美しい織物を織るための、大切な“こと”を変わらず守り続けています。
“合理的な織物ではなく、美しい織物を手掛けたい”
そんな機屋としての誇りと、自分達の感性を信じる道を選んだ滋賀喜と丹波屋。
手織りであること。
西陣で織ること。
素材・意匠に拘ること。
常に新鮮さを求めること。
美しい織物を織るための、大切な“こと”を変わらず守り続けています。